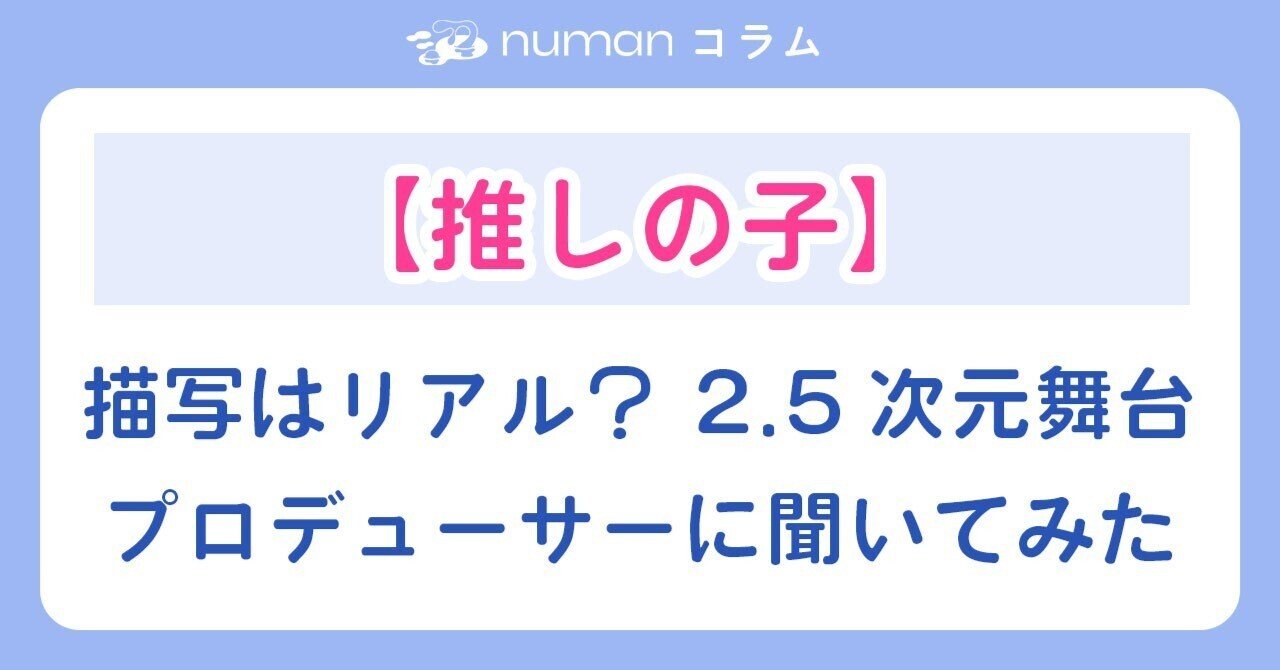
【推しの子】の描写はリアル? 2.5次元舞台プロデューサーに聞いてみた「ララライって大きな劇団なんだな…って冷静に考えちゃいました(笑)」
アニメ【推しの子】第2期は“2.5次元舞台編”が放送中。アクアらが人気漫画を原作とした『東京ブレイド』の舞台に挑む姿をメインとしたストーリーが展開していきます。 本編で挿入される劇中劇は2.5次元舞台を再現したかのような描写があり、稽古風景では“2.5次元役者あるある”などが度々挟まれており、2.5次元舞台ファンや関係者からは「リアルすぎる!」という声があがっているよう。
numanでライターを務めていたこともある、合同会社SrotaStage(※)のプロデューサー・通崎千穂さんに「制作会社によってさまざまかとは思いますが…」という前提で、お話しいただきました。
※合同会社SrotaStage:乙女ゲームや女性向けコンテンツの2.5次元に特化した舞台製作を行っており、ミュージカル『ピオフィオーレの晩鐘』、舞台『CharadeManiacs』、舞台『夏空のモノローグ』などを製作している。

※2024.09.25に公開した記事を一部編集のうえ、転載しています
舞台『東京ブレイド』は「ビジュアルに自信がないとできない見せ方」
【推しの子】第2期1話(第12話)は舞台『東京ブレイド』のいわゆる“オープニング”から幕が開けました。ナレーションの後に、各キャラクターの名前とビジュアルがステージいっぱいに映し出される演出は、実際の舞台を見ているかのようでしたね。
通崎「原作コミックを読んだ時から、“IHIステージアラウンド東京(※)”だー!!と思っちゃいました。それとともに『東京ブレイド』って規模感の大きい2.5次元なんだ……『ララライ』って大きい劇団なんだ……と冷静に考えてしまいました(笑)。
※「ステアラ」の略称で親しまれた円形劇場。東京都江東区に存在したが現在は閉館。
アニメであんなに長尺で舞台のオープニングを見せてくれるとは思わなかったので、いい意味で驚きました。原作マンガのイラストから始まり、そこから舞台キャストを映し出している描写がリアル。あれはビジュアルに自信がある2.5次元舞台でしか出来ないやり方ですが……テンションが上がりますよね。
初めて観た2.5次元舞台のクオリティで、2.5次元というコンテンツの印象が決まってしまうので、舞台に偏見のあったアクアを、まずは1番規模感の大きいステアラに連れて行くというあかねの選択肢は正しいなと思いました。
ただ、アクアはステアラらしい映像演出に感心していましたが、あかねの言う通り『物理的課題を創意工夫でクリアする2.5次元』もとても魅力的なので、あかねがそこに言及してくれたのは嬉しいポイントです」
舞台は圧倒的にコスパが悪い。魅入られた人間だけが残る
【推しの子】第2期1話(第12話)では舞台稽古初日の光景も描かれました。アクアやかならの他、劇団ララライ所属の役者が一堂に会する稽古場では“あるある”が散りばめられていました。
主演クラスは代役を立てることもあるが、あかね曰く「演技人は演技が好きなので、夜だけでも参加しようという人も多い」とのことでしたが、実際の現場の熱量はどのようなものなのでしょうか?
通崎「まず大前提として、2.5次元に限らず、舞台は究極に演劇が好きな人間たちの集まりだと思っています。というのも、映像やアフレコのお仕事と違い、ぶっちゃけギャランティの面だけを考えたら舞台は圧倒的にコスパが悪い。それでも“生のエンタメ”に勝るものはない、と舞台に魅入られた人間だけが最終的にこの業界に残ります。事務所の方針もあるので、本人の意志ではないこともありますが…。
その究極の集合体が、まさにララライのような“劇団”です。最近は “演劇ユニット”や“(俳優の)プロデュース公演”という形も多いですね。2.5次元界隈だとミュージカル『薄桜鬼』などで知られる毛利亘宏さん主宰の「少年社中」が昨年25周年を迎えています。劇団は2.5次元舞台を創るよりはオリジナル作品を上演することの方が多いのですが、最近だと伊藤マサミさんの劇団「進戯団 夢命クラシックス」が『うみねこのなく頃に』の舞台化シリーズを手掛けていますね。
先日、【推しの子】舞台化が発表されましたが、脚本・演出・作詞を担当する中屋敷法人さんも劇団「柿食う客」を主宰している方なので、今作にはぴったりだなと感じました」
「漢字が苦手な演劇人はいます(笑)」大事なのは原作解像度
また、ララライの看板役者である姫川やイケメン俳優のメルトが、かなに漢字の読み方を聞くシーンも。かなが「演劇の人ってなんで漢字読めない人多いの?」と苦言を呈していましたが、これは…?(笑)
通崎「漢字が苦手な子は結構います(笑)。稽古初日の打ち合わせである、いわゆる“本読み”前にこそっと脚本家や原作に聞きに行っている方を見かけます。
ただ2.5次元の舞台においては、漢字を読めるか、学があるかどうかより、原作の理解を深めてから現場に入ってくるキャストの心象が1番いいです。ちゃんと原作をやっていれば、専門用語は読めるはずなので。あと、単語のイントネーションで原作に触れてきたかどうかは結構分かります。
弊社で舞台化している乙女ゲームのような、アニメ化していないコンシューマーゲームなど、原作を履修するハードルが高いものでもしっかり原作に触れてくる人はいて、そういう方は最初から好印象ですね。
また、あかねが言及していた、グループに分かれるというのは現場によるかなと思います。確かによく聞く話なんですが、不思議と弊社の現場ではあまり見かけませんでした。
女性キャストと男性キャストで分かれている印象はありますし、ピンポイントに『この2人、仲がいいんだ』と思うことはありますが、決まったグループに分かれている印象はないんですよね。乙女ゲーム原作という少し特殊な舞台だからでしょうか。
別の会社の制作に入った際、男性キャストだけの現場では3~5人ずつの仲良しなグループがあった気がします。芸歴や年齢が近い子同士が固まる印象でした。キャラクターとしてのグループ分けがある時は、そのグループのキャスト同士でディスカッションしている姿もよく見ますね」
伝言ゲームになるのは否めない…齟齬が生じる場合も
2.5次元舞台編、最初の山場となった原作者・アビ子と舞台制作側のいざこざ。このくだりを見た通崎さんは「胃が痛くなりました…(笑)」と言います。その部分での苦労はやはり大きいようです。
通崎「作品内でも言われている通り、プロデューサーはまず案件を持ってくるのが仕事です。「これを舞台化したらきっと面白い!」と思う作品を企画書にして原作に提出し、許諾をいただくという形です。弊社の場合、そこから脚本家に原作をやり込んでもらうのですが、これが結構時間がかかります。
乙女ゲームは何人ものキャラクターのルートが存在するのですが、脚本家の方には基本的に全キャラクターのルートをフルコンプしてもらうようにしています。脚本家は別案件も並行して書いていたりもするので、読み解く時間も含めて、3か月~長くて半年くらいは時間をとらないといけません。
そうしてプロット、第1稿と出来上がっていくのですが、【推しの子】で描写された通り、間に入る人間が多ければ多いほど伝言ゲームになってしまう、というのは本当にそうだなと。原作サイドからの指摘を少しマイルドな言葉にして伝えてしまって、結果、齟齬が生じてしまった、みたいなことは幾度かありました…申し訳ないです。
一方で現場では、『稽古場は演出家が仕切るもの』という暗黙の了解があります。プロデューサーや脚本家が稽古場に来ても、演出に口出しすることはあまりありません。私の場合は原作愛が強いタイプなので、あまりに“解釈違い”な時は演出に口を出ししてしまうこともあるのですが…。
逆に演出家も脚本家にリスペクトを持っていて、稽古をしてみた結果、脚本で修正したいところがあれば、どういった理由で直したいのかを文章化して脚本家に相談する、というようにしています。こういった時も、プロデューサー、演出家、演出助手、原作、台詞を言うキャスト本人と多くの人間が関わるので、齟齬や誤解が生じることはどうしてもあります。でも「作品をよりよくするためのディスカッションだから!」と前向きに取り組んでくださる方が多いです。
原作者とキャスト、スタッフは仲良くできるの?
1話最後では漫画家の吉祥寺先生とアビ子先生が稽古場に訪れていました。原作者が見学に来ることはよくあるのでしょうか?
通崎「基本的に原作サイドの方には稽古初日の顔合わせ(本読み)、衣装付き通し稽古、ゲネプロには立ち会っていただいたき、加えて日々の稽古動画のまとめを共有しています。
やっぱり原作の方が稽古場に来る時は緊張しますね! いつ稽古場にいらっしゃるのかは事前にキャストに伝えるようにしているので、真面目なキャストは解釈で悩んでいることがあれば、その日までにメモしたり、言語化したりして、当日聞きに行っています。私は誰がそういう動きをしているかも稽古場でよく見るようにしています」
3話(14話)ではアビ子と吉祥寺の対立も。アビ子は「自宅にキャストを呼んでごはん会とかしてるらしいじゃないですか!」と責めるシーンがありましたが、キャストや制作側と原作者の距離感は近いのものなのしょうか?
通崎「コロナ禍前は打ち上げで原作のスタッフの皆様とも話す機会があったのですが、最近はその風習はあまりなくなってしまいました……。【推しの子】でマンガ家の吉祥寺先生がキャストを自宅に招いていましたが、コロナ前はああいった機会もあったというような話を聞いたことはあります。マンガ家さんだと、キャストに色紙を描いてくださる方も多いです。
弊社ではないですが、男性の原作スタッフさん達とキャストでサバゲ―をしたという話を聞いたことはあります(笑)。最近の2.5次元のキャストはオタク気質な方も多いので、キャスト同士も含めてオンラインゲームやカードゲームなどで仲良くなる人もいるようです」
舞台を作る際には原作者、キャスト、脚本家だけではなく多くの人が制作に関わっています。さまざまなプロが愛情とプライドを持って作り上げる2.5次元舞台。それゆえ衝突もあるかもしれませんが、うまくいったときの一体感は凄まじいものなのでしょう。
(企画・執筆:三鷹むつみ)
いいなと思ったら応援しよう!
 よろしければ応援お願いします!
より読者の皆さんへ喜んでもらえるコンテンツ作りに還元します!
よろしければ応援お願いします!
より読者の皆さんへ喜んでもらえるコンテンツ作りに還元します!
