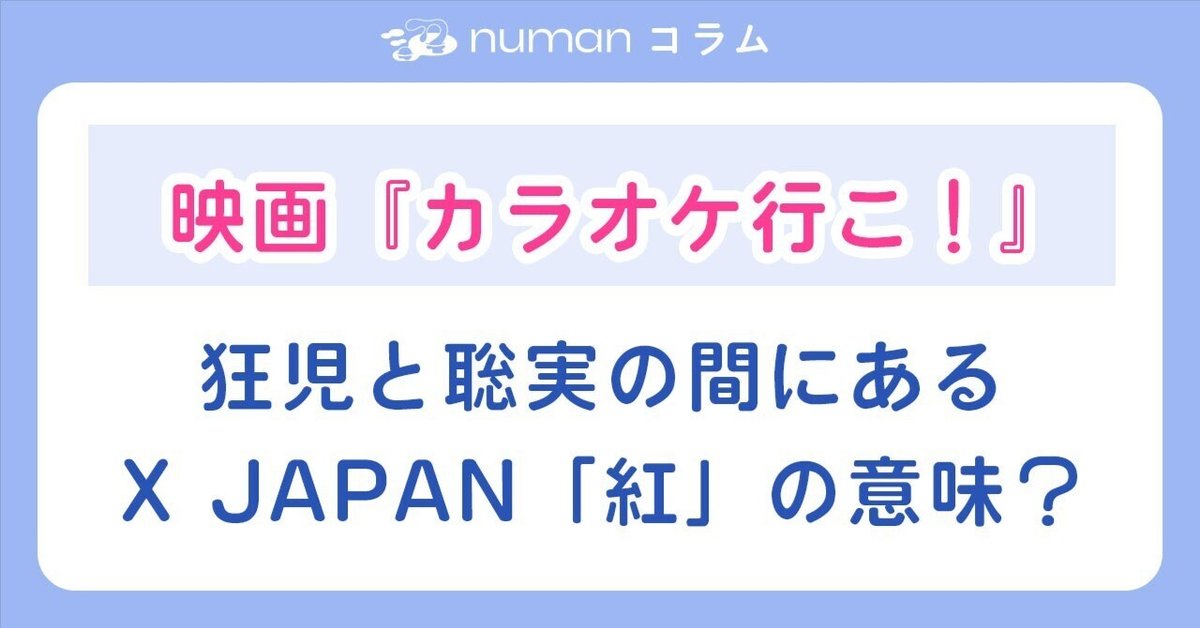
映画『カラオケ行こ!』狂児と聡実の間にあるX JAPAN「紅」の意味。歌詞の先にある、二人が出した答え
2024年1月12日に公開された映画『カラオケ行こ!』は、『女の園の星』や『夢中さ、君に』で知られる和山やまさんの同名漫画を原作とした実写化作品。主演には綾野剛 と齋藤潤 がキャスティングされ、二人の不思議な関係が物語の中心として描かれています。
ある事情で歌を上手くなりたいヤクザの成田狂児 (綾野剛)が、森丘中合唱部部長である岡聡実 (齋藤潤)に出会い頭に「カラオケ行こ」と誘うところから始まります。 原作ではX JAPANの名曲『紅』を狂児が熱唱するシーンはギャグ的にサラリと描かれているのですが、映画版では『紅』が物語の中心に据えられているように感じられるほど、執拗に狂児が歌うカラオケの場面が繰り返されます。
異なる世界に住む狂児と聡実。同じ時間を過ごしお互いのことを知っていく中で、二人の間には、言葉では表せない感情が存在することを感じさせる瞬間が何度もあります。
本稿では、劇中で繰り返される『紅』が狂児と聡実の間の関係性にもたらす意味について考察していきます。
※記事の特性上、内容に触れています。

※2024.09.17に公開した記事を一部編集のうえ、転載しています
『紅』が狂児と聡実の関係にもたらす意味
まず、映画『カラオケ行こ!』は基本的に聡実視点で描かれるため、聡実の心情を多く読み取ることができます。
聡実は基本的におとなしく冷静沈着に見えますが、中学生らしく抑えきれない感情の起伏を持ち合わせていることが行動から読み取れます。特に合唱への想いは人一倍持っていて、それゆえに変声期を迎えた苦しさや、合唱部の後輩からの大きすぎる憧れに対する葛藤も強く、より不安定にさせているように見えました。
そんな聡実が抱えていたあらゆる葛藤が、ある日狂児に向けて一気に爆発します。「スケベのアホカス!狂児のドアホ!」と激高しながらも「元気が出るもの」としてしっかりとお守りを投げつける姿は、思春期の不安定さがよく出ているなと感じました。
このように聡実が全ての葛藤を狂児に向けた一方で、悩みを打ち明けたのも狂児だけでした。
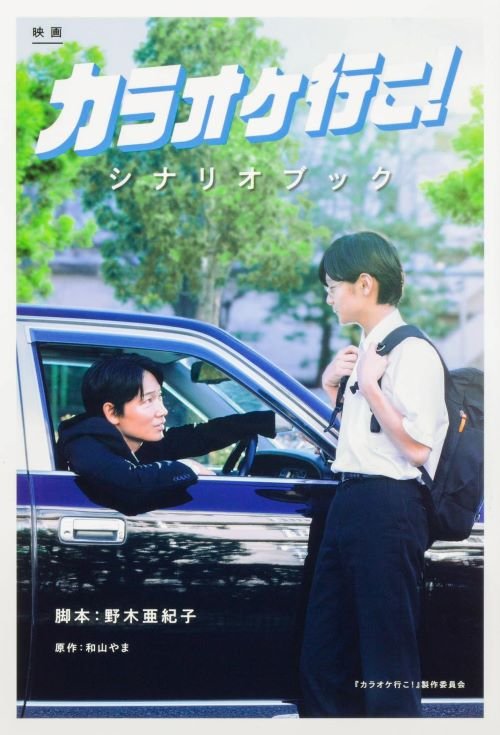
いつの間にか聡実にとって狂児は、学校や家庭と無関係の信頼できる大人として、次第に全ての感情を向ける存在となっていったのかもしれません。
『紅』は曲を通して「大切な誰かを失った痛み・悲しみ」を歌っています。歌詞には俺(=置いて行かれた人)とお前(=去ってしまった人)の二人の登場人物の存在を感じさせます。
「『紅』が二人の関係を象徴しているとすれば、聡実にとって狂児は「大切な誰か」です。しかし、狂児にとっての聡実はどうなのか、聡実自身がひっかかりを覚える瞬間も訪れます。 聡実の感情が爆発し狂児にぶつけたあと、「ごめん」と連絡してきた狂児に対して聡実は「もう知らん。本番まで一人でカラオケしてください」と突き放します。
「ばーか、慌てとけ」と独りごちり聡実ですが、狂児はあっさりと承諾してしまいます。 その連絡を無表情で見つめる聡実。実はこの時、彼はかなりショックを受けたのではないか、と感じました。
中学生のちょっとした意地っ張りに対して大人がサッと引く、という構図のため、大人からすれば狂児の対応は妥当です。
しかし「自分がいなくなったら焦るのが当たり前」だと思っていた中学生の聡実からすると、そんな狂児の大人の対応の表面だけ受け取ってしまい「自分の存在はそこまで必要とされてないのかも」とショックを受けることは自然なことだと感じます。 聡実の中で自己完結してしまった感情のアンバランスさが、『紅』における「置いて行かれた人」と「去ってしまった人」という二人の運命を予感させ、少し不穏な空気が漂い始めるのです。
狂児と聡実の『紅』に対するそれぞれの答え
『紅』の歌詞に沿うなら、二人は永遠に会えなくなり、聡実は狂児のマボロシを追い続けることになるでしょう。しかし、映画では『紅』を受けいれて、それを超えた二人それぞれの答えを導き出しています。
狂児が死んでしまったと勘違いし、狂児の代わりにヤクザのカラオケ大会で『紅』を熱唱する聡実。紅に染まった聡実の姿を、狂児が何か悟ったような表情で見つめます。歌い終わったあとに生きている狂児の姿を見て驚いた聡実へかけた言葉は「聡実くんを置いて死なれへんしな」。
この言葉は「去ってしまった人」として描かれた狂児の「去るわけないでしょ」という至極簡単な『紅』に対する答えです。 そして、聡実側も『紅』への答えを見つけます。

カラオケ大会の後、狂児とは結局連絡が取れなくなってしまいます。聡実の同級生から「マボロシだったんちゃうん」と言われてしまうほどに、狂児とそれを取り巻く環境も徐々に消えてしまいました。狂児の痕跡を探すため、共に過ごした場所をめぐり、まさに『紅』の歌詞のように狂児のマボロシを追い続ける聡実。
ようやく一つの痕跡を見つけた聡実は「おったやん」と嬉しそうに呟きます。たとえもう会えなくなっても、一緒に過ごした時間がマボロシではなかったと確信できれば、それで十分だ、とでも言うかのように。
これもまた「置いて行かれた人」として描かれた聡実による『紅』への答えだと思います。 狂児と聡実はそれぞれ自分の世界のことをよく知っていて、お互いが「本当は関わってはいけない」ということも、少しのきっかけで会わなくなる可能性が高いことも理解していました。だからこそ、一緒に過ごした時間が”ピカピカ”であり、次第にお互いに存在になったのでしょう。
狂児と聡実の間にある感情がどんなものなのか、観た人によって感じ方は変わると思います。ですが、お互いに「大切な人」だと思っていたということだけは『紅』の文脈が教えてくれているのです。
『紅』に込められた想いを共有するための二人の共通点
とはいえ、二人は本来であれば“ヤクザと中学生”、“大人と子供”という異なる立場からもわかるように、狂児と聡実には共通点がほぼありません。お互いの気持ちを察することもできず、言葉だけがかろうじて通じている状態です(真意が伝わっているかは不明ですが)。
そんな二人には、実は一つだけ大きな共通点があります。それは、二人が共通して話すことができる唯一の言葉、つまり“関西弁”です。
「あんたが去ったとき 俺は振り返られへんかった ハートがめちゃ痛い 追いかけ続けてしまいそうで怖い あんたのマボロシ見てもうて 真実見つけに真っ暗な街を走ったで 記憶の中のあんたは 俺の心の中で光ってるで ピカピカや」

ある日、聡実が『紅』の冒頭の歌詞を和訳したものを関西弁にし、それを狂児が読み上げるという場面があります。それぞれの生活や感情に深く結びついた関西弁で語られる『紅』の強い想いは、よりストレートに二人へ染みわたり、そしてその深さに共感するのです。
この場面は結局ギャグに転じてしまうのですが、聡実は狂児の『紅』の思い出に愛と悲しみを匂わされた時から「愛とは?」「狂児とは?」と考えるようになります。 そんな風にお互いを繋ぐ要素となっていた『紅』と共通点である関西弁が繋がったこの瞬間こそが、二人の結びつきをより強固にしたのではないでしょうか。
映画では『紅』が強調されていますが、原作では異なる描写もされており、二人の関係性もまた少しだけ異なります。映画と原作の両方を楽しむことで、和山やまワールドの魅力をより深く堪能できるかと思います。ぜひその違いを感じ取りながら、二人の物語に浸ってみてください。
(執筆:宮本デン)
いいなと思ったら応援しよう!
 よろしければ応援お願いします!
より読者の皆さんへ喜んでもらえるコンテンツ作りに還元します!
よろしければ応援お願いします!
より読者の皆さんへ喜んでもらえるコンテンツ作りに還元します!
